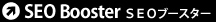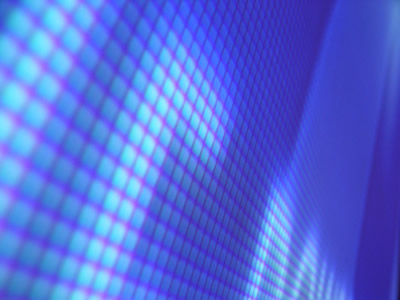サイト内の<title>タグや<h>タグ(h1~h6)などのHTMLの構造や、キーワードの数や関連性など、検索エンジンの順位結果に影響を与える自サイト内の要因のことです。
タイトルタグやMETAタグの内容、HTMLの構造、ページ内のコンテンツのボリュームやキーワードの比率などがSEOに影響する主な要素と思われます。
これらの内部要因を最適化し、検索エンジンのロボット(クローラー)にうまく認識されることで上位表示に有効的に働くといわれていますが、内部要因はサイトオーナーがコントロールしやすく、一時期、ユーザーには見えないキーワードの詰め込みなどを行う等の行為が蔓延したため、外部要因に比べてその影響が少なくなってきていましたが、最近では、以前よりも影響が出てきていると考えられています。
検索エンジンアルゴリズムとは、キーワードに対するサイト順位を決める際に用いる処理ロジックのことです。
ページ内のキーワード比率や被リンク数、サイトの構造など、数百以上のアルゴリズムを組み合わせて、総合的に順位付けを行っているといわれています。
現在日本においては、ヤフーもグーグルの検索アルゴリズムによって検索結果を表示していることから、実質グーグルのアルゴリズムに沿った対策を行うことがSEO対策の重要な内容になります。
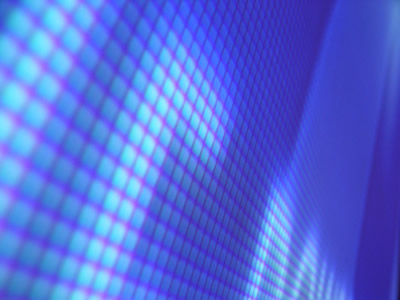
サンドボックスとは、新しいドメインで制作されたサイトが、一時的に上位表示ができなくなってしまう現象のことです。
SEO対策を行い上位表示をされた後、しばらくすると順位が落ちてしまい、その後、数週間から数ヶ月すると検索結果に再び表示されるような現象です。
ドメインエイジと関係しており、新しいドメインは有益な情報提供しているかどうか様子を見ている状態とされているといわれています。
しかし、最近では、逆に新しいドメインがサイトオープン後しばらく上位に表示され、1ヶ月程度で適正な順位になるといわれており、スパム判定等で一時的な大幅な順位下落以外では影響が少ない現象だと思います。
自サイトから他のページへリンクをすることを初リンクといいます。
発リンクは、サイト運営者がコントロールできるため、SEO施策において被リンクほどの重要性はありませんが、あまりにも変な発リンクをつけると順位が下がることがあります。
また、グーグルは1サイトからの発リンクの数を、使いやすさから、適切な数に抑える ことを進めており、100未満が望ましいといわれています。
発リンクに対して、別のサイトからリンクされることを被リンク、お互いのサイト同士でリンクしあうことを相互リンクといいます。
Yahoo!が自社で開発した検索エンジンのアルゴリズムです。
YSTの検索エンジンのアルゴリズムは、全くのゼロから構築されたものではなく、買収などによって獲得したInktomi、AlltheWeb、altavistaといった検索エンジンのアルゴリズムを統合した形で作り出したものです。
米国のヤフーが中心にアルゴリズムを構築しており、そのアルゴリズムをヤフージャパンが日本向けにカスタマイズしています。
グーグルに比べて、人的な評価が入っていると考えられ、場合によっては不可解な検索結果になってしまうことがよくあります。
日本では、2011年にグーグルとの検索エンジン分野での技術提携が発表され、実質的にはグーグルのエンジンをヤフーも使うようになったため、YST独自のアルゴリズムはほとんどないと思われます。
ウェブページへ「いつ・どこから・だれが・どのくらい」アクセスしているのかを把握することをアクセス解析といいます。
SEO対策の評価やサイトの評価などを判断する上で非常に重要な手法になります。
アクセス解析では、サーバ上のログ(履歴)を元に解析を行いますが、専門的な内容でかつ、可視性がわるいため、通常、アクセス解析ソフトやツールを使用します。
様々なアクセス解析ツールがありますが、最もメジャーなのが、Googleが無料アクセス解析ツールとしてリリースしている「google analytics」があり、商用のアクセス解析ツールと変わらないか、それ以上の高度な分析が可能で、多くの企業に取り入られています。
http://www.google.com/intl/ja/analytics/
ホームページ中に特定のキーワードがどれくらい出現して存在しているかを表す%のことをキーワード出現率といいます。
キーワード出現率=キーワード出現回数÷単語数で計算するが、キーワードの出現回数と単語数に、テキスト表示以外の部分の要素(alt内やMETA内のキーワード)や接続詞、助詞などの要素も含むかで変わってきます。
キーワードの詰め見込みによる検索順位UPの手法が横行したため、意味のないコンテンツのサイトが上位表示された時期があったため、キーワードを連呼するような文章や、出現率が高すぎる場合はスパムとして判断されることがあるので、3%~5%の間ぐらいがよいとされています。
HTMLの画像タグに代替テキストをつける属性です。
画像にアンカータグをつける場合、aタグで囲まれた範囲にテキストを入れないため、リンクのアンカーに何も入らないことになるため、テキストリンクよりもSEO的に不利になります。
そのため、altタグ内にテキストを入れることでアンカーテキストと同じような役割を果たすことができますし、画像の内容を読み込めない検索エンジンに画像部分の情報をテキストとして渡すことができます。
しかし、SEOを意識しすぎてaltにキーワードなどを詰め込む等のことをすると、評価が下げられてしまう可能性がありますので注意が必要です。
書籍の目次にあたる見出しを定義するHTMLタグのことです。
H1から見出しの階層順にH6までの6段階があります。
H1タグやh2タグの中にターゲットとするキーワードを入れることでSEO的に効果があるといわれますが、H1は各ページの大見出しにあたるもので、1ページあたり、1つしか使用できません。
そのため、h1やh2の見出しタグを乱用することで検索エンジンの評価が下がることがあるので注意が必要です。
また、CSS等でSEO効果が高い見出しタグを見えなくする、文字を著しく小さくしてキーワードを詰め込むといったこともあまり望ましくありません。
見出しの階層構造がh1→h2→h3→h4→h5になるのが正しい使い方なので、h2タグではさまれた文章の後に、h1が来るのは、間違った使い方になります。
SEO的にも、見やすさからも文章構造や内容に矛盾がないように使うようにする必要があります。