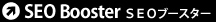Googleが特許を取得しているホームページの重要度を表す指標です。
ページのリンクポピュラリティや更新頻度、リンクのカテゴリー属性、ドメイン年齢などを元に指標化されていますが、現在では、ページランクの高いサイトが上位表示のサイトというわけではありません。
一時期は、有名ページのページランクが変動するたびにインターネット上のニュースサイトなどで取り上げられていました。
最近は重要度が下がったともいわれますが、被リンク元の評価として、まだまだ重要な指標になっています。
政府系や公共団体、非営利団体等のサイトは一般的にページランクが高くなっています。
SEOに重要な別の指標としてトラストランク(Trust Rank)という指標もあります。
SEOとは、検索エンジン最適化(Search Engine Optimization、サーチ・エンジン・オプティマイゼーション)の略で、検索エンジン上で特定のキーワードで検索した検索結果ページの上位に表示させ、サイトへのアクセスを増やす施策や方法のことです。
現在、検索エンジン経由でサイトを閲覧するユーザーは、インターネットを利用するユーザーの80%以上といわれています。
そのため、検索エンジンの検索結果表示の上位に表示されればされるほど、ユーザーがそのサイトにアクセスする数が大きくなります。
逆に検索結果の3ページ目(上位20サイト)以降のサイトへのアクセスは極端に低くなる傾向があるため、SEOはインターネット上の集客を促進する方法として、Webサイト運営上、重要な要素になっています。
グーグルもヤフーも検索エンジンにおけるサイトの評価について、具体的な評価基準は公開されていないため、(大まかな方針などは公開されています。)世に出回るSEO対策は、様々な検証の結果としてのもので、中には噂レベルやでまかせもあります。
インターネット上のコンピュータを特定するための住所を示す記号です。
それぞれのドメインは世界に1つしかないもので、www.xxxx.comやwww.sss.co.jpといった文字列で表記されます。
www.xxxx.comなどのドメインで、www部分の任意の半角英数字にすることで、サブドメイン(例:sub.xxxx.com)を作ることができます。
ドメインの名前自体がSEOにも影響するといわれていますが、それほど影響は大きくないと考えられています。
また、ドメインが取得されてからどのぐらいの時間がたっているかがSEOに影響するといわれ、取得してから時間のたつドメインは、新しいドメインよりも信頼性が高いとして、高値で取引されるケースがあります。
検索エンジンのインデック情報やアルゴリズムを含むサーバは複数のサーバに分散されているため、検索順位結果を更新した際にサーバごとに更新タイミングが異なります。
そのため、グーグルダンスとは、更新処理が行われている間は、アクセスするサーバによって結果が少しずつ異なるため、その間は、数時間や数日で順位が変動してしまう現象のことです。
最近は、グーグルでは大幅なロジックの変更以外では、数日で検索順位の評価を出しており、グーグルはリアルタイムはアルゴリズム評価とインデックス生成を行うことを目指しているため、サーバ間での変動はそれほどありません。
ヤフーの検索エンジンで、トップページのみインデックスから削除される、あるいはサブページの検索順位に比べ、著しくTOPの順位が低くなる現象のことです。(1000位ぐらい下になるなど)
2007年秋ごろからこういったサイトが急増しており、一部のSEO会社はTDPからのリカバリーサービスというのも行っていました。
一説にはヤフー検索エンジンのバグとも言われており、1ヶ月から2ヵ月後のインデックス更新で戻ることも多いが原因はあまりわかっていなかったのですが、グーグルとヤフーが検索エンジンで事業提携してからは、明確なスパム判定をうけない限りは、原因不明なTDPは減ってきました。
現在では、ヤフーの検索エンジンにグーグルの検索エンジンをしているため、明確なペナルティ以外のTDPはほとんどないと考えられています。
画像やFlash、JavaScriptやプログラムからの呼び出しなどと関係しない、単純なHTMLのテキストリンクのことです。
グーグルやヤフーは、そのページの内容を見るときに、テキスト部分の情報を収集するため、その際にテキストリンク(アンカーテキスト)に記載されているキーワードを重点的に評価することがわかっています。
例えば、アダルトサイトでは、”18歳以下”というテキストリンクの遷移先の多くがヤフージャパンのサイトになっているため、検索エンジンで”18歳以下”というキーワードで検索するとTOPにヤフーのページが表示されます。
そのため、SEO対策を行いたいキーワードを含んだテキストリンクからの被リンクが有利とされています。
HTMLページのHEADタグに挟まれた部分に記述するタグで、ページに関する情報を記すものです。
METAタグ情報は、検索結果や検索結果の表示に影響があるが、実際のサイト上には表示されません。
代表的なMETAタグにkeywordとdescriptionというのがあり、SEOに重要な要素でしたが、keywordsについては最近では、キーワードつめこみなどを行うスパム行為が多いため、影響力は少なくなっています。
descriptionについては、検索結果の表示時に影響があるため、文字量を100文字程度にして、実際のコンテンツとの関連性の高い内容を入れることで、検索結果の表示をある程度調整することが可能です。
リンクを貼るタグのことをアンカータグといい、で表され、に挟まれたテキストをアンカーテキストといいます。
グーグルは、被リンクの際にアンカーテキストの内容を見ており、SEOというキーワードに対して、”SEO対策”というアンカーテキストでの被リンクと、”こちら”でのアンカーテキストの被リンクでは、前者の方が有効になります。
たとえば、18歳未満で検索すると、ヤフージャパンのサイトがTOPに出てきますが、アダルトサイトで、18歳未満というアンカーテキストで、ヤフージャパンにリンクされているためです。
画像等にアンカータグをつけた場合、アンカーテキストが存在せず、画像の内容を検索エンジンのプログラムは読めないため、imgタグのaltを代わりに読み込むとされています。
関連する多数の専門サイトやポータルサイトなどから引用されたりすることで、リンクポピュラリティが高いブランド化されたサイトのことです。
明確な基準があるわけではありませんが、オーソリティサイトは信用度やPageRank、検索結果の表示順位が高い野が特徴です。
検索エンジンには、サイトを評価する基準でオーソリティ性(=信頼性)という評価があるといわれており、サイトの構造や被リンクの質、あるいは、コンテンツの内容などがユーザーにとって信頼性が高いかを評価してします。
SEOには、外部要因として被リンクが重要とされていますが、同じ数の被リンクでもオーソリティサイトからの被リンクは、特に効果が高いとされています。

動的ページとは、プログラムによって、アクセス時に自動生成されるページのことです。
通常、閲覧者がアクセスするたびにプログラムで作った雛形にデータベースから呼びだした情報を埋め込むような作りをしているため、URL に『?』や『&』などの変数を含むため、検索エンジンがクロールしにくく、SEO対策には不向きとされていましたが、最近では、徐々に認識されるようになってきており、前ほどのデメリットはありません。
また、サーバーによっては、mod_rewrite などを利用して、動的なページを静的なページに見せることができるため、そういった設定を行うことで影響を軽減できます。
静的ページとは、動的ページと対して、実際のHTMLファイルなどがサーバ上に存在し、そのままの形で表示できる一般的なhtmlページをさします。
ロボットがページを辿った際に収集されやすく、SEOに適しているとされています。